家族が加入・脱退するとき
- 手続き
- 解説
- よくある質問
家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
| 必要書類 |
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 備考 |
|
被扶養者の認定日について
| 理由 | 認定日 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 子どもが生まれた場合 | 出生日 | 原則5日以内 |
| 入社時に扶養家族がいる場合 | 入社時に届出の場合…被保険者の資格取得日と同日 | 原則5日以内 |
| 入社時から遅れて届出…健康保険組合の受理日 | 原則14日以内 | |
| 新たに扶養する場合 | 健康保険組合の受理日 | 原則5日以内 |
- 新たに扶養するときの注意事項
-
- 所定の申請書および必要添付書類一式が提出され、健康保険組合で扶養の事実が確認できた日を認定日とします。
※遅れる場合は、事前に健康保険組合へご相談ください。
事象発生日から30日以内に届け出のあった場合は、別途判断させていただきます。
(事象発生日を証明・確認できる書類が必要です。) - 認定日前に医療機関にかかられても当組合では給付できません。
- 所定の申請書および必要添付書類一式が提出され、健康保険組合で扶養の事実が確認できた日を認定日とします。
家族を扶養からはずすとき
被扶養者となった方が、その後、生活・生計状況等が変化して、健康保険の被扶養者資格を失うことがあります。被扶養者の認定条件からはずれる場合は、すみやかに手続きをしてください。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 就職 収入オーバー |
被扶養者が就職して、勤め先の健康保険に加入したり、収入が増えて被扶養者としての認定条件からはずれた場合 |
| 失業給付受給開始 | 被扶養者が雇用保険の失業給付受給開始になった場合 |
| 別居 | 被保険者と同居していなければ被扶養者として認められない人が、別居によって被扶養者からはずれた場合 |
| 結婚 | 被扶養者が結婚して、結婚相手の被扶養者になった場合 |
| 離婚 | 配偶者と離婚して、被扶養者からはずれた場合 |
| 死亡 | 被扶養者が死亡した場合 |
| 後期高齢者 | 被扶養者が75歳(一定の障害があると認定されたときは65歳以上75歳未満)になった場合 (健康保険組合の被扶養者資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者となります) |
| 必要書類 |
|
|---|---|
| 該当する被扶養者の資格確認書(交付されている場合) | |
| 高齢受給者証(交付されている場合) | |
| 備考 |
|
扶養からはずす手続きを忘れたとき
扶養からはずす手続きを怠って、誤って当健康保険組合の保険診療を受けた場合、その期間、健康保険組合が負担した金額を返金していただくことになります。忘れずに手続きを行ってください。
被扶養者の削除日について
| 理由 | 削除日 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 後期高齢者の場合 | 75歳の誕生日当日、又は65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定を受けた日 | 原則5日以内 |
| 死亡した場合 | 死亡日の翌日 | 原則5日以内 |
| 上記以外の扶養削除の場合 | 健保の受理日 | 原則5日以内 |
- 注意事項
-
- 扶養からはずれた方は、国民皆保険制度(全国民が必ずいずれかの公的医療保険に加入)により、他の被用者保険または国民健康保険に加入することになっています。
- 国民健康保険に加入するには「健康保険資格喪失証明書」が必要です。
- 「健康保険資格喪失証明書」が必要な方は、異動届の理由欄に「資格喪失証明書希望」と明記してください。
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者の範囲
被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害年金を受給できる程度の障がいのある方は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
| 被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
|---|---|
|
|
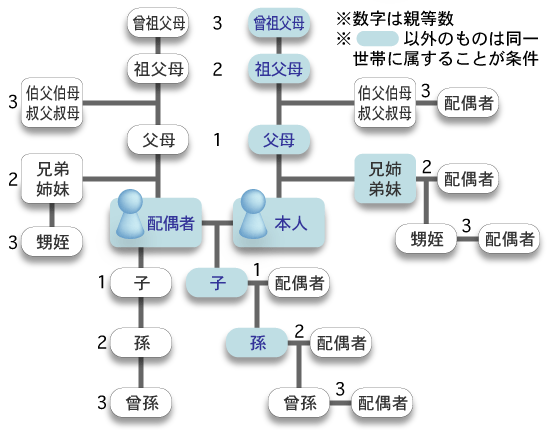
被扶養者資格の調査
当健康保険組合では保険給付適正の観点から、定期的に被扶養者確認調査を行っております。
被扶養者の方が、その後も被扶養者の基準を満たしているかを確認するためのものです。
その結果、認定基準を満たしていないと判断した場合には、判定した日から被扶養者の資格が取り消しとなります。
扶養に該当していない人を認定していることは、健康保険組合の財政に影響を及ぼし、保険料が増加するなど、被保険者の方々への負担増につながります。
調査時には調書をはじめ添付書類等を提出していただくことになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く
-
2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。
